札幌の遺言・相続手続き・成年後見のご相談は/行政書士法人エニシア

>遺言・相続・成年後見サポートセンター トップ>よくある質問>遺言の質問2
 遺言を書いたことや、その内容を子供たちには知られたくありません。
遺言を書いたことや、その内容を子供たちには知られたくありません。
自分で遺言を書こうと思っていますが、どのような点に注意して書け
ばいいのでしょうか?

自分で法的に有効な遺言書を作るためには、遺言者が遺言の全文(遺言内容・日付・署名)
を自分自身で書く必要があります。代筆やワープロでの作成は認められていません。
① どのような紙に書いてもかまいません、またどのような筆記具を用いてもかまわないこと
になっています。しかしながら、大切なメッセージを残す為のものですので、ある程度の
耐久性のある用紙に、ボールペンなど簡単に書き直し(変造)できない筆記具を使うべき
です。
② 「遺言書」といった表題がなくても、内容で確認できれば遺言書としては有効ですが、
「遺言書」「遺言状」といった表題があった方が明確です。
③ 書き方は、縦書き・横書きどちらでもかまいません。数字表記については、アラビア数字
(1,2,3・・)でも漢数字でもかまいませんが、不動産表示や金額などを書く場合は
誤認や変造を防ぐ意味で、多角漢数字(壱、弐、参・・・)を使うとよいでしょう。
④ 誰に何を相続させる、遺贈するのか、はっきり特定できるように書く必要があります。
土地や建物など不動産を記載する場合は、住居表示ではなく、登記簿謄本の表示通りに
記載してください。
⑤ 遺言書は2枚以上になる場合はステープラーやのりなどで綴じ、契印を押します。
(契印がなくても、内容に同一性があれば有効とされていますが、トラブルを防ぐ
意味でも押した方がよいでしょう)
⑥ 日付は必ず具体的な年月日を記入してください。「8月吉日」などは日付が特定できず
遺言が無効になってしまいます。
⑦ 署名については、その人を特定できれば、雅号などでもいいことになっています。
一般の方は、戸籍上の氏名を書く方がよいでしょう。
⑧ 署名と合わせて、押印します。印は三文判でもかまいませんが、実印を押す方が望ましい
でしょう。
⑨ 遺言書を封筒に入れ、封をしたり封印をすることは、必ずしも要求されていませんが、トラ
ブルを防止する意味でも封印をお勧めします。なお、遺言書については家庭 裁判所で
開封(検認)しなければなりません。遺言書を発見した相続人等が開封してしまわないよう
に、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」などと記入しておくのが良いでしょう。
⑩ 遺言書を書き間違ってしまった場合は、厳格な方式に従って訂正を行わなければ
なりません。この方式に従っていないと、訂正が無効となってしまうので注意が必要
です。できれば最初から書き直しをした方が無難です。
>遺言の質問2 ページトップ

自筆証書遺言を書くときの注意点は?
 遺言を書いたことや、その内容を子供たちには知られたくありません。
遺言を書いたことや、その内容を子供たちには知られたくありません。自分で遺言を書こうと思っていますが、どのような点に注意して書け
ばいいのでしょうか?

自分で法的に有効な遺言書を作るためには、遺言者が遺言の全文(遺言内容・日付・署名)
を自分自身で書く必要があります。代筆やワープロでの作成は認められていません。
① どのような紙に書いてもかまいません、またどのような筆記具を用いてもかまわないこと
になっています。しかしながら、大切なメッセージを残す為のものですので、ある程度の
耐久性のある用紙に、ボールペンなど簡単に書き直し(変造)できない筆記具を使うべき
です。
② 「遺言書」といった表題がなくても、内容で確認できれば遺言書としては有効ですが、
「遺言書」「遺言状」といった表題があった方が明確です。
③ 書き方は、縦書き・横書きどちらでもかまいません。数字表記については、アラビア数字
(1,2,3・・)でも漢数字でもかまいませんが、不動産表示や金額などを書く場合は
誤認や変造を防ぐ意味で、多角漢数字(壱、弐、参・・・)を使うとよいでしょう。
④ 誰に何を相続させる、遺贈するのか、はっきり特定できるように書く必要があります。
土地や建物など不動産を記載する場合は、住居表示ではなく、登記簿謄本の表示通りに
記載してください。
⑤ 遺言書は2枚以上になる場合はステープラーやのりなどで綴じ、契印を押します。
(契印がなくても、内容に同一性があれば有効とされていますが、トラブルを防ぐ
意味でも押した方がよいでしょう)
⑥ 日付は必ず具体的な年月日を記入してください。「8月吉日」などは日付が特定できず
遺言が無効になってしまいます。
⑦ 署名については、その人を特定できれば、雅号などでもいいことになっています。
一般の方は、戸籍上の氏名を書く方がよいでしょう。
⑧ 署名と合わせて、押印します。印は三文判でもかまいませんが、実印を押す方が望ましい
でしょう。
⑨ 遺言書を封筒に入れ、封をしたり封印をすることは、必ずしも要求されていませんが、トラ
ブルを防止する意味でも封印をお勧めします。なお、遺言書については家庭 裁判所で
開封(検認)しなければなりません。遺言書を発見した相続人等が開封してしまわないよう
に、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」などと記入しておくのが良いでしょう。
⑩ 遺言書を書き間違ってしまった場合は、厳格な方式に従って訂正を行わなければ
なりません。この方式に従っていないと、訂正が無効となってしまうので注意が必要
です。できれば最初から書き直しをした方が無難です。
>遺言の質問2 ページトップ

 行政書士 村上佳雅 |
行政書士法人 エニシア TEL 011-212-1895 FAX 011-212-1894 札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F E-mail : info@murakami-office.net [営業時間] 9:00~20:00 [休業日] 毎週日曜・祝日 ※休業日も予約により対応いたします。 |
|
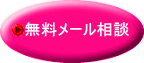
 社員行政書士 村上佳雅
社員行政書士 村上佳雅